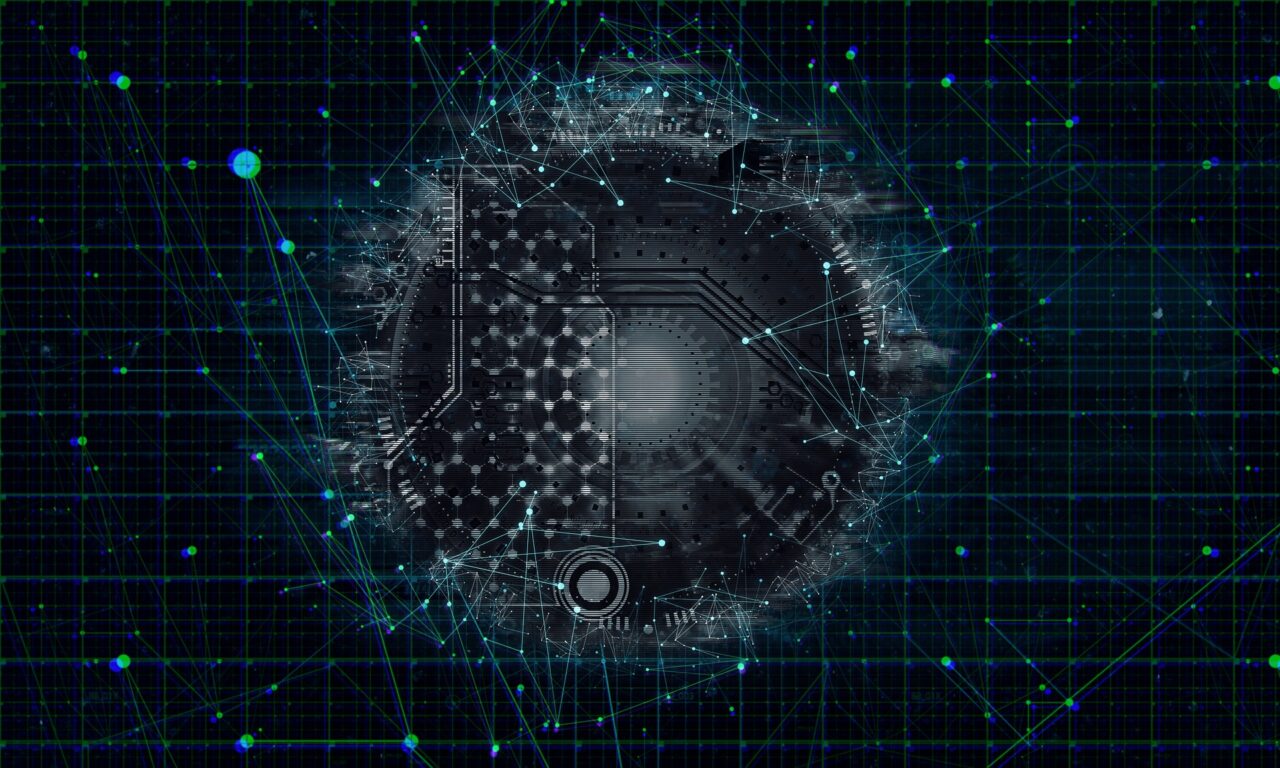相続税はどのように課せられるのか
相続税は、遺産の全額に対して課されるわけではありません。税金が課されるのは、課税される遺産総額から「基礎控除額」と呼ばれる一定額を差し引いたあとの金額です。遺産が基礎控除額以下であれば非課税となり、基本的に相続税の申告や納税は必要ありません。また、基礎控除額を上回っても配偶者控除など他の制度を利用することで、実質的に相続税がかからなくなることや軽減されることがあります。
課税される財産、課税されない財産
相続税の課税の対象となる財産と、ならない財産があります。
| 課税の対象となる財産 | 土地・家屋・借地権、現金、預貯金、有価証券、貴金属・宝石・骨とう品・美術品、貸付金、特許権・著作権などの相続財産、生命保険金、死亡退職金などのみなし相続財産、相続開始前3年(7年)以内の贈与財産、相続時精算課税制度の適用を受けたもの |
| 課税の対象とならない財産 | 墓地、仏壇、祭具などや生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、死亡退職金などの非課税枠(500万円×法定相続人の数)、国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した財産、慈善、学術など公益事業に使ってもらう財産 |
基礎控除額
相続税には基礎控除が設定されています。課税価格が基礎控除額より少ない場合(課税遺産総額が0の場合)には相続税はかかりません。基礎控除の額は以下の計算式で導き出されます。民法で定められた被相続人(亡くなられた方)の相続財産を相続する権利を有する法定相続人の数が多くなれば、基礎控除額は多くなります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告・納税期限
相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。遅れると延滞税などのペナルティが課せられることがありますので、注意が必要です。